ガルシア・マルケス「百年の孤独」ようやくの読了。半分手前まで読んだあたりで去年9月、自転車で実家からアパートに戻る途中夕立にあって、鞄の中の本もびしょ濡れになってぶよぶよに膨らんでしまった。ようやく乾いて頁がめくれるようになってから、少し読みかけては別の本を手に取ってを繰り返してようやくゴールに辿り着く頃には正直最初の方の話は頭から抜けかけている。
さらに同じ名前を二代目、三代目と引き継ぐ上に途中一気に増殖(同じ名の息子が17人)したりでもう誰がどのアウレリャノやら、池澤夏樹監修の読み解き支援キットという栞(書店で配布されていた)の助けをもらってさえ、容量の足りない自分の頭では混乱しかない。初代のホセ・アルカディオ・ブレンディアを筆頭に、男も女もみんなして狂ってて、初代の妻であるウルスラ婆さんだけがかろうじてまともに近そうには見えるのだけど、次世代以降が次々と死を迎える中、ひょっとしてこの人だけ話の最後まで生き残るのか、不死身なのかと不安にさえなってくる。
一つ一つの出来事の意味を把握しようとしなくてもいいやつだ、とこの物語への自分の距離の取り方がつかめたのも、そのウルスラ刀自の退場する辺りへきてようやくのこと。物語の辻褄を追わずに「神話」の一種のようにただ読み流していくと、ものすごくしっくりくるのだ。神話というものが家族(<民族、国家)の伝承の物語なのだから、拡大解釈だとしてもそう外れてはいない、ということにして。羊皮紙やらサンスクリット語やらと革命やストライキといった社会情勢が同居した時空の歪んだような世界に充満する、家族という矮小な単位を超えた「血脈」の生臭み。
話は少し逸れるけれど、学生時代という随分昔の話だが、同じくガルシア・マルケスの小説の「予告された殺人の記録」の映画版について、たまたま近い時期に観たデニス・ホッパー監督・主演の「ラスト・ムービー」となぜかセットで自分の中に記憶されてしまっている。舞台を南米、と一緒くたに捉えるのもどうかと思うけど、どちらの映画も狂騒状態になった集団に主人公が追われ、終には呑み込まれていくシーンが恐怖で、あちらは集団トランスしやすい風土なのだろうか、とかいう偏見がその2作品の映画のせいで少なからずインプットされてしまったのだが、果たして実際のところどうなんだろう。
ちなみに「ラスト・ムービー」は「予告された~」(1987年)よりもかなり以前の1971年の作品。
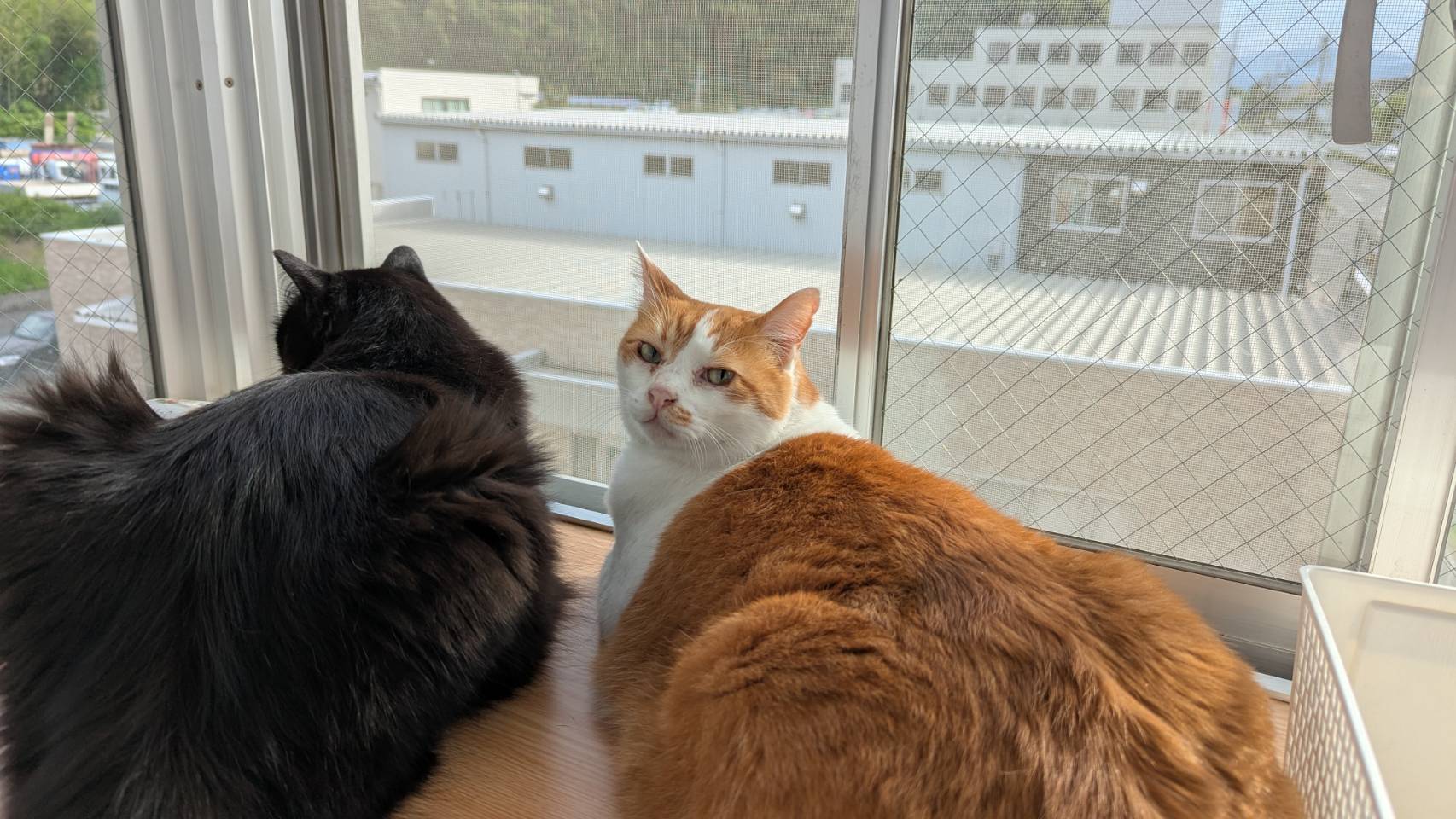


コメント